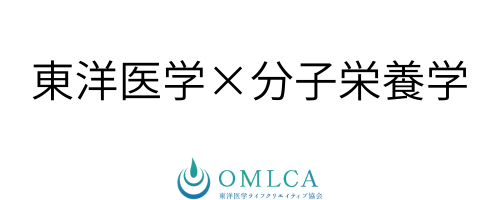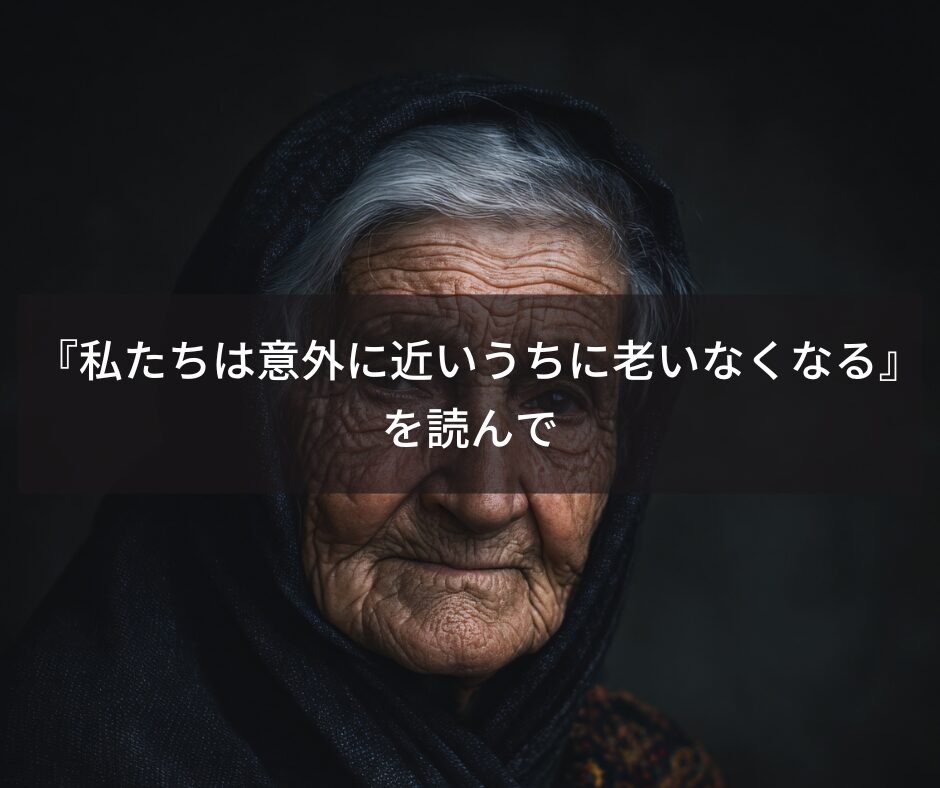—東洋医学 × 分子栄養学から“老い”を考える—
最近、『私たちは意外に近いうちに老いなくなる』という本を読みました。
老化研究の最前線を、オートファジーを専門とする吉森 保先生がわかりやすくまとめた一冊で、読み終えたあと「この内容は、分子栄養学や機能性医学の観点と驚くほど相性が良い」と強く感じました。
そして東洋医学の視点を重ねてみると、老化という現象がどれだけ“多層構造”で起きているのかがよりクリアになります。
今日はその3つの視点を統合して、「老いはどこから始まり、どう向き合うべきか」ということについて書いてみたいと思います。
老化は“情報の乱れ”であり、可逆的である
この本で最も印象的だったのは、老化は「細胞の情報システムの劣化」であるという新しい考え方でした。
細胞は年齢を重ねても、若い頃と同じDNAを持っているのに、なぜ老いるのか?
それは DNAの「読み方(エピゲノム)」が乱れ、細胞が本来の役割を忘れていくから だといいます。
つまり、老化というのは細胞の劣化ではなく、細胞の情報システムの劣化だということ。
ということは、不可逆的ではなく可逆的だということになります。
これはとてもオモシロい考え方です。
分子栄養学や機能性医学でも同じ話
じつはこのことは、僕がやっている分子栄養学や機能性医学にも通用します。
- 慢性炎症
- 糖代謝異常
- 栄養欠乏
- ミトコンドリア機能低下
こうした要因がDNAの修復をオーバーワークにさせて、エピゲノムの乱れを招く——という理解は、機能性医学が長年研究してきた内容と一致します。
機能性医学というのは、僕がいままで皆さんに紹介してきた分子栄養学(ある意味で分子栄養学は機能性医学の「食部門」といえます)をも包括する考え方で、元々は「慢性疾患をいかに根本的に治すか」を目的にして始まった比較的新しい医学です。
ということは、機能性医学や分子栄養学の知見を使うことでDNAの修復を正常化させることができ、結果的に老化はある程度抑制することができるということになります。
東洋医学でいえば「精・気・神の乱れ」
ところで、東洋医学では老化は次のような原因で起こると考えられています。
- 腎精の消耗
- 気(生命力)の不足
- 神(精神)の不安定
これは現代医学的に言い換えれば、ホルモン、ミトコンドリア、自律神経系および脳機能の衰えが原因ということになります。
例えばこのなかの腎精について東洋医学的な分類に則してみてみると、腎精の枯渇はDNA修復力の低下であり、腎陽虚はミトコンドリアの熱産生の低下(冷え)であり、腎陰虚は慢性炎症・酸化ストレス増加、腎気虚はATP不足ということになると思います。
東洋医学では老化を“ミトコンドリアと修復力の低下”として直感的に捉えていたと考えられます。
つまり、老化=生命情報の統合性の低下という考え方は、西洋医学でも東洋医学でも共通しているわけです。
栄養の乱れは「老化のアクセル」
分子栄養学の立場から見て、老化を最も加速させる要因のひとつが NAD+の低下 です。
NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)は、エネルギー産生やDNAの修復、さらにはサーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)の活性に欠かせない分子なんですけど、30代を過ぎる頃から急速に低下することがわかってきています。
さらにここに高血糖、慢性炎症、過度のストレス、アルコールの過剰摂取などの要因が加わると、DNAの修復にNAD+が過剰に使われて、結果的に枯渇してしまいます。
これが「加速度的な老化」の正体なんです。
ビタミンB₃(ナイアシン)は体内でNAD+に変換され、NAD+合成の必須原料です。
つまりビタミンB₃の摂取不足や過剰な消耗が老化を加速させる原因になるということですね。
機能性医学的には
機能性医学では、糖化(AGEs)、酸化ストレス、ミトコンドリアの機能障害、腸内環境の悪化などが老化の“主要ドライバー”として扱われています。
これらはすべて、NAD+とミトコンドリアを大量に消費する原因になっています。
AGEsとは「終末糖化産物(Advanced Glycation End products)」の略で、体内の過剰な糖とタンパク質が結びついて生成される「老化物質」のことです。
これが体内に蓄積すると、老化を促進したり、動脈硬化、糖尿病の合併症、白内障など様々な病気の原因になったりすると考えられています。
例えばHbA1cという血液検査項目がありますが、これはヘモグロビンと糖が結びついで離れなくなった糖化ヘモグロビンの割合を測っているものです。
この割合が増えたのが糖尿病ですね。
この糖化という現象は、主にタンパク質と糖がくっついてしまうことで起こりますが、例を挙げるとフワフワの食パンをトースターで焼くとキツネ色でポロポロのパンに変わりますが、これがいわゆる糖化現象(メーラード反応)で、カラダのなかでこれが起こるとそれが老化につながるというわけです。
トーストしたパンは美味しいですけど、体内や臓器が焦げてボロボロになるのはちょっとイヤですよね(笑)
東洋医学では「脾が弱ると全身の老化が早まる」
東洋医学では、栄養の消化吸収力の低下、それによるエネルギーの低下、さらには気血の不足によって体の修復力が落ちると考えます。
このことは栄養全般について言えることで、そもそも栄養が不足する大きな原因は①摂取が不足する、②摂取しても吸収ができない、③摂取して吸収できても過剰に浪費している、という3つです。
東洋医学でいう“脾虚(消化吸収を担う臓である脾の機能低下)”は、現代医学でいうタンパク不足、エネルギー産生にかかわるビタミンB群の不足、それらに起因するミトコンドリア機能の低下、さらに進んで起こる慢性疲労などと同じ状態を意味しているわけです。
つまり脾が弱って消化吸収力が落ちると、全身の老化が早まることになるわけです。
身体に足りないものは食事などを通して摂り込むしかありませんし、気をつくるには気の材料を摂ってそれがしっかりと吸収できるようにすることが必要ですし、つくることができたら浪費しないような生活をすることが大事ってことです。
老化を遅らせる食事・生活習慣
それでは老化を遅らせるにはどうしたらいいのでしょうか?
この本を読んで感じたのは、「老化を遅らせる方法」は難しいものではなくて、むしろ日常の生活習慣の延長線上にあるということです。
具体的に本書では、カロリー制限や断続的ファスティング、運動、NAD+前駆体の摂取などが紹介されています。
これらを分子栄養学・東洋医学で整理すると以下のような形になります。
ひとつめは、食べない時間を少しつくること。
断続的断食(インターミッテント・ファスティング)といって、例えば夜8時に食べたら翌朝の10時頃までは食べない、など“胃腸を休ませる時間”を確保する方法です。
これは単に「食べない」ということではなく、体の中の“お掃除スイッチ”が入って、古い細胞が片づけられたり、血糖のコントロールが整ったりすることを期待しています。
東洋医学でも同じで、「脾胃(消化器)を休めることは気を整えて元気を養う」とされていて、数百年前から行われてきた養生法とある意味で重なります。
ふたつめは、地中海食のような“体に負担の少ない食事”を取り入れることです。
地中海食とは、魚、野菜、豆、果物、オリーブオイルなどを中心にした食事のことですが、これは現代医学では「炎症を抑える食事」として知られ、老化のスピードをゆっくりにすることが研究でも示されています。
東洋医学的に見てみると、このような食事は「血を養い、体に熱や湿をためにくい食事」ですよね。
体の内側で“サラサラ感”を保ち、不要な負担をかけない、非常に理にかなった食べ方です。
そして三つめが、筋肉や回復力の土台となる栄養をきちんと摂ること。
特にタンパク質が不足すると、年齢とともに筋肉が落ちて、疲れやすくなり、代謝も落ちてしまいます。
また、ビタミンB群やマグネシウム、魚油(オメガ3)などは、体を“若く保つための働き”を静かに支えてくれる栄養素です。
東洋医学でいう「腎を養う」というのは、まさにこの回復力の土台づくりのことだと思います。
腎は成長・生殖・ホルモン・老化に深く関わる臓と考えられていて、ここが弱ると“老化”を感じやすくなります。
老化は“整えることができる現象”になってきた
こうした習慣をまとめてみると、特別なことをしなくても老化の進み方を緩やかにできる、ということが見えてきます。
老化は突然やってくるのではなく、毎日の積み重ねの中で少しずつ方向が決まっていきます。
逆に言えば、今の生活を少し整えるだけで、その方向を変えることができるということです。
これは東洋医学が昔から伝えてきた「未病」という考え方とも完全に一致します。
体はいつも何らかのサインを出しています。
疲れやすい、むくむ、眠りが浅い、冷える、イライラしやすい、肌のハリが落ちた——こうした変化は、老化がどの方向に進んでいるのかを教えてくれる“シグナル”です。
私が行っている 東洋医学ドック では、血液データ(分子栄養学・機能性医学)にくわえ、脈診・舌診・腹診(東洋医学)を組み合わせることで、あなたの体が「どちらに傾き始めているのか」を立体的に読み解きます。
老化は止めることはできませんが、スピードをゆるめることは確実にできます。
そして、そのための方法は“難しいこと”ではなく、今日から取り入れられるものばかりです。
気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
今回はこの辺りで。