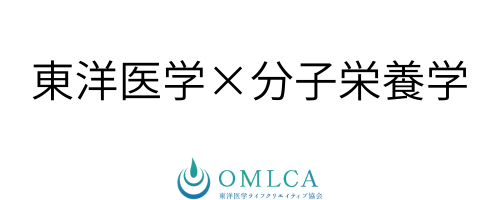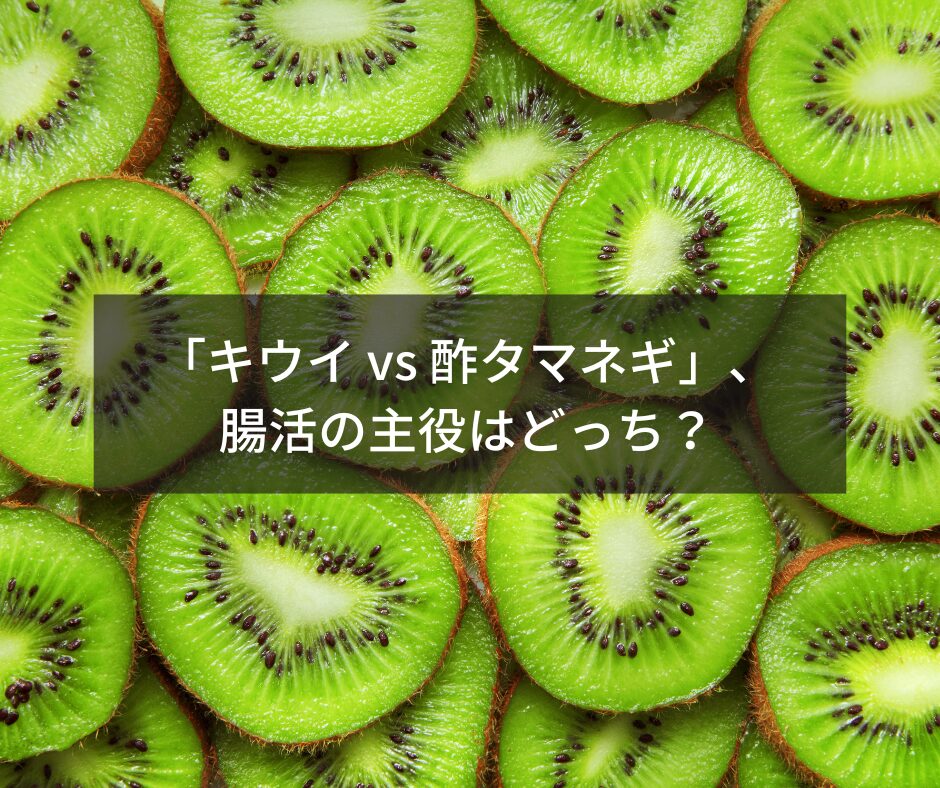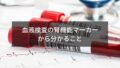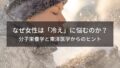―東洋医学と分子栄養学で読み解く“腸を整える”ということ―
「キウイを食べれば腸が健康になる?」の真実
最近、『キウイを食べると腸が健康になる!』(松生恒夫著)という本を読みました。
タイトルからしてインパクト抜群ですけど、内容は意外と科学的で、「食物繊維」「酪酸」「腸内細菌」「睡眠」などのキーワードが並んでいます。
要は――キウイに含まれる水溶性・不溶性の食物繊維が腸内細菌を育て、短鎖脂肪酸(特に酪酸)を増やし、腸のバリア機能を高めるという話。
これ、分子栄養学の観点から見ても非常に理にかなっているんです。
ただし、いつも言っているように「誰でも健康になる“魔法の食べ物”はない」ということだけはシッカリと覚えておいてくださいね。
つまり、キウイが合う人もいれば、逆に体を冷やしてしまう人もいる、ということ。
同じ食材でも、体質によって「薬」にも「毒」にもなるんです。
ここが、東洋医学と分子栄養学が交わる面白いところです。
東洋医学で見た“キウイ”の性質
東洋医学では、キウイは「寒性」で「甘酸味」という性質を持っていて、熱を冷まし、体の潤いを補う果物とされています。
つまり、胃熱や便秘傾向のある方には合いやすいんです。
一方で、冷え性、胃腸が虚弱、下痢気味の方が毎日食べたりすると、逆にお腹を壊す原因にもなりかねません。
これは東洋医学でいうところの「気虚」で、分子栄養学的にいえば「代謝や消化力が低下している状態」といえます。
そんな方には「酢タマネギ」や「ぬか漬け」などの、温性かつ発酵の力をもつ食材の方が合うことが多いんです。
分子栄養学で見た“腸内リズム”の整え方
分子栄養学の視点では、腸は「免疫・ホルモン・神経」の中枢的存在です。
さらに言えば、腸内フローラのバランスを崩す原因は、食事だけでなくストレス、睡眠不足、冷えなどもあります。
実際『キウイを食べると腸が健康になる!』の中でも、「腸を温める」「良質な睡眠を取る」「ストレスを減らす」ことなどが強調されています。
つまり腸を整えるとは、単に何を食べるかということではなく、どう生きるかのリズムを整えることでもあるんです。
キウイも酢タマネギも、あなたの体質次第
キウイの酵素(アクチニジン)はタンパク質の消化を助け、酢タマネギの酢酸は腸内のpHを整えます。
どちらも素晴らしい食品ですが、どちらが「最適」かは人それぞれ。
「冷えやすい」「疲れやすい」「朝スッキリ出ない」などの体のサインを見ながら、自分の腸に合った“整え方”を選ぶことが大切です。
あなたの“腸のタイプ”を知ることから始めませんか?
腸内環境は、気・血・水のバランス、そしてミトコンドリアの働きにも関係しています。
あなたのカラダはいま、どんな状態なのか?
キウイが合うのか、酢タマネギが合うのか――。
その答えは、検査やカウンセリング、東洋医学的な四診なしには見えてきません。
僕がやっている「東洋医学ドック」では、舌診・脈診・腹診に加え、分子栄養学的な問診や検査を組み合わせて、あなたの「腸・自律神経・代謝」を多角的に診たてています。
「腸を整える」とは、ただ“食べ物を変える”ことではない
多くの人が「腸活=ヨーグルトや食物繊維を摂ること」と思いがちですが、東洋医学の世界では、“腸”は単なる消化器官ではなく、気・血・水の流れを反映する臓腑の一部とされています。
つまり、腸の乱れは「気の滞り」「冷え」「ストレス」など、体全体のバランスの乱れとして現れます。
便秘も、下痢も、ガスも、実は“体質の鏡”です。
ですから、腸を本当に整えるには、食材の「陰陽」や「五性(寒・涼・平・温・熱)」を理解し、自分の体質と自分を取り囲む環境(気候や地域特性など)に合わせて食を選ぶことが大切なんです。
キウイが合う人、酢タマネギが合う人
『キウイを食べると腸が健康になる!』という本でも紹介されているように、キウイは豊富な食物繊維とポリフェノール、消化酵素のアクチニジンを含みます。
腸内細菌に“エサ”を与えるプレバイオティクスの効果もあって、便秘の改善も期待できます。
ただし、東洋医学的にキウイは「寒性」なんです。
冷え体質や下痢傾向のある方が毎日食べると、逆に腸の蠕動が弱まり、お腹が張る原因になることもあります。
一方、酢タマネギは「温性」。
血流を促し、体を温め、脾や胃の働きをサポートしてくれます。
特に「冷えるとお腹が痛くなる」「朝は体が重い」「疲れやすい」などのタイプには、酢タマネギの方が腸に優しく働きます。
つまり、同じ“腸活”でも――
- 冷え体質なら「温める腸活」
- 熱体質なら「冷ます腸活」
というように、方向性が逆になるということ。
分子栄養学で見る「腸タイプ」と代謝の関係
一方で分子栄養学の視点では、腸内環境はビタミン・ミネラル・ホルモン・神経伝達物質の代謝に密接に関わります。
腸に炎症があると、セロトニンやGABAなどの“幸せホルモン”がうまく作られず、気分の波や自律神経の不調にまで影響してしまいます。
実際、腸を整えると「よく眠れるようになった」「イライラしなくなった」「肌がきれいになった」という声も多く聞かれます。
それは、腸が全身の代謝リズムの“司令塔”だからです。
つまり、腸活は美容的な効果もあり、メンタルケアにもなり、“全身を再起動をする”役割もあるんです。
腸を整える生活習慣 〜東洋医学×分子栄養学からの提案〜
腸を整えるための生活習慣の基本的な提案をしてみましょう!
まずは、下の表にあげる生活習慣を実践してみてください。
| 習慣 | 効果 |
| 🌿 朝は白湯からスタートする | 胃腸を温め、消化酵素の働きを高める |
| 🌿 毎日同じ時間にトイレに行く | 排便リズムを整える |
| 🌿 夜22時までに就寝する | 成長ホルモンと腸粘膜の修復サイクルを整える |
| 🌿 発酵食品+食物繊維をセットで摂る | 善玉菌の餌と菌体を同時に補給 |
どんなに良いサプリや食材でも、生活のリズムが乱れていれば腸は整いません。
じつは“腸活”とは、食ではなく生き方を整えることなのです。
あなたの「腸タイプ」をチェックしてみませんか?
こうしたサインが出ている方は、腸だけでなく、脾・肝・腎のバランスが乱れている可能性があります。
僕の東洋医学ドックでは、舌・脈・腹の診察に加え、分子栄養学的検査(血液・栄養バランス分析)を組み合わせ、「あなたの腸タイプ」を分子栄養学的+東洋医学的に可視化します。
- 食後にお腹が張る
- 冷えると下痢しやすい
- 便秘と下痢を繰り返す
- 朝起きてもスッキリしない
- 甘いものをやめられない
腸から“気・血・水”を整える、新しい健康のかたちへ
東洋医学では「脾胃は後天の本」と言われます。
つまり、食べる力・消化する力・吸収する力こそが健康の土台だということ。
先天的なもの(遺伝的素因)だけですべては決まらないことを数千年前から知っていたんですね!
キウイが合うのか、酢タマネギが合うのか――
それは、あなたの体が今どんなバランスで生きているかを映す“鏡”にすぎません。
体質を知り、自分に合った腸の整え方を見つけること。
それが、本当の意味での「未病を防ぐ」第一歩です。
東洋医学ドック
腸・自律神経・栄養バランスをトータルに診たてる“あなた専用の腸活ドック”
👉 詳しくはこちらから