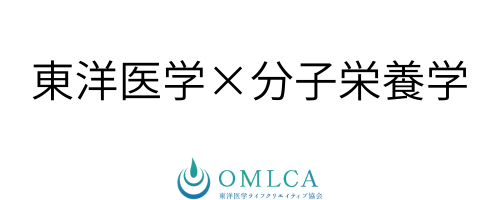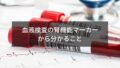突然ですが、ラーメンは好きですか?
飲んだ後によく食べますか?
ラーメンはいかにもカラダに悪そうなイメージの食べ物ですけど、どの辺が悪いのか、どうすれば少しでもカラダに良い食べ方になるのか、飲んだ後にどうしてラーメンが食べたくなるのかなどについて、真剣に考えてみました(笑)
ラーメンと死亡リスクに関する論文
世の中にはいろいろな研究をしている人たちがいますが、ラーメンと死亡リスクについて調べたり考えたりしている人たちもいるんです。
もちろんこれ、日本の論文です。 英語で論文の原文を読みたい方はこちらから。
この論文は、山形県立米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科講師の鈴木美穂氏らによるもので、山形コホート研究の食物摂取頻度調査票のデータを使って、日本人の一般集団におけるラーメンの摂取頻度と死亡リスクとの関連について検討したものです。
ラーメンの摂取頻度別に死亡リスクが上昇する集団を特定したとして、J Nutr Health Agingに報告されました。
先行研究には、人口当たりのラーメン店舗数と脳卒中の年齢・性調整後死亡率に正の相関が示されているものがありますが、摂取頻度と死亡リスクの関連についてははじめての報告です。
ベースラインの背景を見ると、ラーメンの摂取頻度が高い群ほどBMIが高値で、男性、若年層(70歳未満)、喫煙者、飲酒者が多く、スープを半分以上飲む割合や糖尿病、高血圧の割合も多かったとされています。
結論的なことだけピックアップすると、以下のようになります。
- ラーメンの摂取頻度の高さは、男性、若年層、BMI高値、喫煙、飲酒、糖尿病、高血圧と関連していた
- スープを半分以上飲む人や飲酒者で、最もリスクが高かった
男性の若年層で飲酒および喫煙者がスープを半分以上飲むと、死亡リスクが高くなる傾向があるようです。
なんとなく頷ける感じですかね?
この論文では、スープに含まれる塩分やアルコールの摂取がラーメン摂取と死亡リスクとの関連を強めることを示唆していると結論付けています。
分子栄養学的には、ラーメンの問題点は塩分以外では、炭水化物メインで糖質プラス脂という太りやすい組み合わせなことと、麺類一般に言えることですけど噛まないで飲み込む傾向が強いことなどだと思っています。
もう少しラーメンとカラダの関係について深掘っていきましょう!
締めにラーメンが食べたくなる理由
皆さんもそうですか? 飲んだ後に、無性にラーメンが食べたくなりますか?
じつは、これにはちゃんと理由があります。
ヒトの血液中のブドウ糖濃度(血糖値)は、下がりすぎたり上がりすぎたりしないように厳密にコントロールされています。
これが破綻すると糖尿病や低血糖になるわけです。
上がりすぎの糖尿病ばかり病気として注目されているけれども、分子栄養学では低血糖にとても注目していて、私の患者さんでも多く目にする病態です。
話をラーメンに戻しましょう(笑)
お酒を飲むと、アルコールはカラダにとって毒なので、(解毒の中心的な臓器の)肝臓がこれを解毒しようとします。
毒はカラダの中にあるとダメなので、この作業は優先度が高いんですね。
血糖値が下がったときに、これを上げるための糖新生という働きがあるんですけど、ここでも肝臓が中心的な役割を担っています。
肝臓ってとっても仕事量が多いんです。
ところが肝臓にとってアルコールの解毒は最優先なので、糖新生に手が回らなくなります。
だから、お酒を飲むと低血糖になるわけ。
するとカラダは何とかして血糖値を上げたくなって、炭水化物がメインのラーメンが食べたくなるんです。
もちろん、血糖値が上がるならスイーツでも菓子パンでも甘いジュースでもいいんですけどね。
ただ、他にもラーメンを求めてしまう理由がいろいろあります。
アルコールを飲むと一過性にインスリンの分泌を促進することが分かっています。
つまり、血糖値がより下がりやすくなるわけです。
また飲酒によって食欲を刺激するグレリンというホルモンの分泌が増えることも報告されています。
だから「炭水化物+脂質」という最強の高カロリー食への欲求が高まるわけです。
まだまだあります(笑)
アルコールは抗利尿ホルモンを抑制します。
つまり利尿作用があるわけ。
尿への水分や電解質の喪失によって、カラダは塩分を求めるようになります。
これには、ラーメンのしょっぱいスープが最適なんですね。
さらにアルコール代謝(解毒)では、肝臓のメチオニン回路・グルタチオン合成が促進されます。
特にシステインやグリシンなどのアミノ酸が消費されるために、うま味成分のグルタミン酸を含む食品を欲しやすい傾向になります。
この点でも、旨味の多い醤油や味噌を使ったラーメンスープがベストということなんです。
「締めラー」の東洋医学的な理由
東洋医学ではアルコール(酒)は「辛甘・熱性」とされます。
「辛」は、気血を巡らせるけれど、熱を生みやすい傾向にあります。
また「甘」は、補益をするけれども、過ぎると湿を生じる傾向にあります。
そして、熱性なので体内に熱を生みやすいんですね。
お酒を多く飲むと、以下のようなことが起こります。
甘味によって脾胃の運化機能を弱め、湿を停滞させ、熱性によって肝火や胃熱を亢進させます。
この二つが合わさって 「湿熱」 という病理状態をつくります。
湿熱は、口渇・顔面紅潮・頭重・胃のつかえ感・べたついた舌苔、翌日の二日酔いなどの症状として現れやすいです。
この湿熱をさばくために、体内で起こってくる欲求について考えてみましょう。
塩味は「腎」に入るとされ、堅陰・清熱・軟堅散結などの作用があります。
つまり、体内にこもった熱を冷ますしますし、また水分代謝を助け、湿をさばく作用があります。
そのため、塩辛いスープ(ラーメン)が欲しくなるわけです。
それから小麦は、「甘・涼」に属し、心・腎・脾に入るとされます。
甘味は緊張を緩め、気を補います。 涼性は、熱を鎮める作用です。
特に小麦には「安神(精神を落ち着ける)」作用があるとされています。
だから、飲酒後のほてり・落ち着かなさ・不安定感などを和らげる役割を持っていると解釈することができます。
東洋医学的にみても、ラーメンは飲酒後のカラダの状態の回復のために必要ということになります。
ただし、この記事では飲酒後にラーメンを食べることを推奨しているわけではありませんので、そこのところは誤解しないようにしてください(笑)
分子栄養学および東洋医学的なラーメンの正しい食べ方
それでは最後に「締めラー」の正しい食べ方についてまとめておきます(笑)
大前提として、アルコールを飲みすぎないこと。
長時間飲むとアルコールの摂取量が多くなり、それによって低血糖の時間が長くなるので、余計に締めラーに頼りたくなるからです。
それから、飲酒中は水分をこまめに摂ること。
理由はわかりますよね。
もしラーメンを食べるのなら、スープは全部飲まないこと!
多少は飲んでもいいけど半分以下にしましょう。
家に帰ってからカップ麺をつくって食べるくらいなら、ラーメン屋に寄っていった方がまだましです。 カップ麺には添加物や悪い油がたくさん使われているので、注意が必要ですね。
麺類は飲み込んでしまいがちで消化に悪いので、なるべくよく噛むこと。
まぁ、個人的にラーメンをよく噛んで食べるくらいなら、食べないほうがマシですけどね(笑)
要は、締めラーが必要な状態にしないようにするのが賢明です。
まとめになっていないですけど、今回はこの辺で。
僕のやっている栄養カウンセリングの東洋医学ドックについては、こちらから。
オンラインでも受診できます!