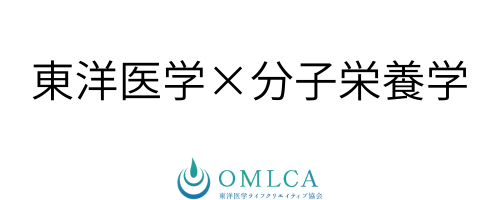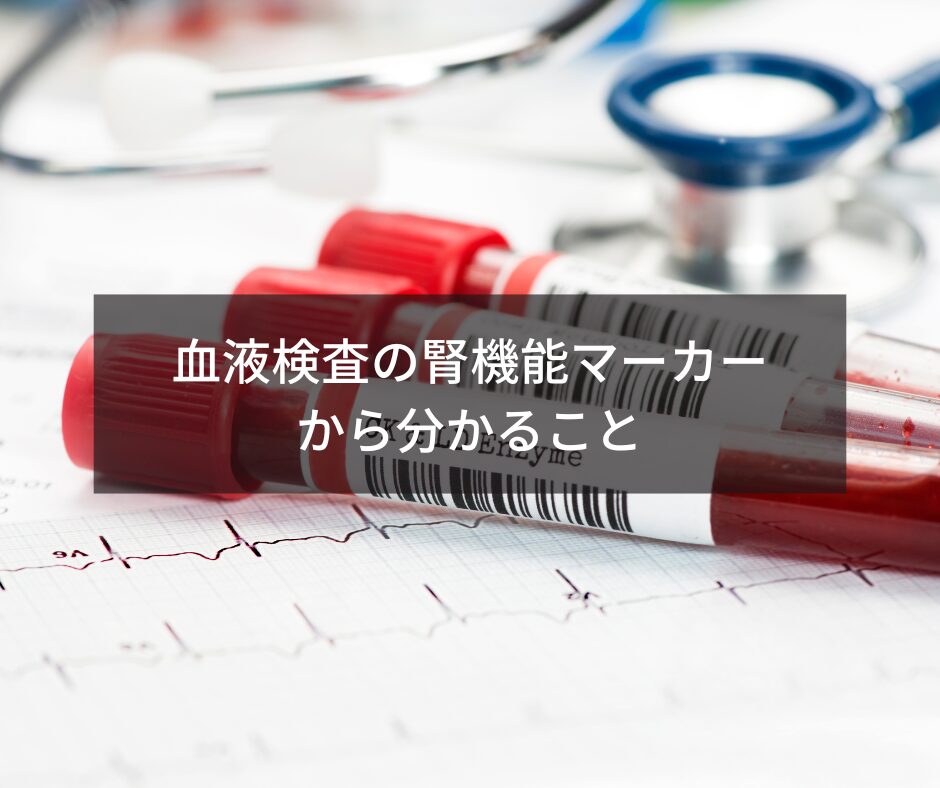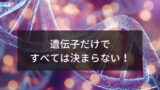病院で健康診断、人間ドックなどを受けると、「腎機能」を調べるための血液検査が行われます。
でもじつはこれらのデータから、腎臓に異常があるかどうかだけではなく、筋肉量や栄養状態、さらには脱水の有無まで推測できることを知ってますか?
今回は、腎機能の指標としてよく使われるクレアチニン(Cr)と尿素窒素(BUN)について、分子栄養学と東洋医学の両面から深掘っていきたいと思います。
クレアチニンからわかること
クレアチニンは、筋肉の代謝によって生じる老廃物です。
腎臓から排泄されるために、腎機能の指標としてよく使われます。
以下に簡潔に標準医療における基準値と低値・高値で想定されることをまとめておきます。
- 基準値(一般的な臨床検査値)
男性:0.7~1.2 mg/dL
女性:0.5~0.9 mg/dL - クレアチニンが低い場合
- 筋肉量が少ない(高齢者・運動不足・長期臥床など)
- タンパク質摂取不足(低栄養・過度なダイエット)
- クレアチニンが高い場合
- 腎機能低下(老廃物が排泄できない)
- 高タンパク食やプロテインの過剰摂取
- 筋肉量が多い人(ボディビルダーなど)では一時的に高くなることも
BUN(尿素窒素)からわかること
BUNは、タンパク質を分解した際に出る老廃物です。
タンパク質は、他の三大栄養素である糖質、脂質とちがって、ゴミが出るので代謝が面倒なんです。
これも腎臓から排泄されます。
こちらについても、以下に簡潔に標準医療における基準値と低値・高値で想定されることをまとめておきます。
- 基準値:8~20 mg/dL
- BUNが高い場合
- 高タンパク食
- 脱水(体内の水分不足で濃縮される)
- 消化管出血など
- BUNが低い場合
- タンパク質不足
- 肝機能低下(尿素を合成できない)
BUN/Cr比でわかること
BUNとクレアチニンは単独で見るだけでは分かることに限界があるので、比率(BUN/Cr比) を見ると原因の推測がしやすくなります。
以下に標準医療での見かたを簡単に挙げておきます。
- 基準値の目安:10~20
- 20以上
- 脱水(血液が濃縮してBUNだけが上昇)
- 消化管出血や高タンパク食でも上がることあり
- 10未満
- 肝機能障害(尿素をつくれない)
- 高度な腎不全
ここまでが、(標準医療の)臨床的によく使われるクレアチニン、BUN、BUN/Cr 比の基本的な読み方です。
これだけだとあまり面白くありませんよね!
でも、分子栄養学や東洋医学の視点から見ると、実はもっと深い意味が見えてきます。
「低クレアチニン=腎精の消耗」
「高BUN/Cr比=津液不足」
といった考え方ができるんです。
ここから先は、分子栄養学的な栄養指導のポイントや鍼灸師にも役立つ「腎精」と腎機能のつながりについて、さらに詳しく書いていきます。
分子栄養学・機能性医学の視点から見る腎機能
ここまででご紹介した クレアチニン や BUN は、単なる「腎臓の働きの指標」としてだけでなく、栄養状態(特にタンパク摂取)や筋肉量を反映するマーカーとしても非常に重要です。
タンパク質はリサイクルする働きが存在するとはいえ、体のさまざまな構造の原料になっているとても重要な栄養素なので、血液データから読み取ることができると有益です。
- 低クレアチニン
- 筋肉の材料となるタンパク質や必須アミノ酸の不足を示すサインです
- タンパク質の摂取不足が続くと、筋肉だけでなくホルモン・酵素・免疫の働きも低下してしまいます
- 食事の内容からも摂取量が不足しているかどうかを判断する必要があります
- 高BUN、高BUN/Cr比
- 脱水や腎臓への負担を示すことが多い項目です
- 水分摂取が足りていない、あるいは塩分・電解質のアンバランスが背景にある可能性があります
このように血液検査の数値は、栄養・生活習慣・代謝の状態を映し出す「鏡」なんです。
東洋医学における「腎精」とのつながり
東洋医学では、腎は単なる排泄器官ではなく、生命力の源である「腎精」 を蓄えていると考えられています。 簡単に説明を加えながら、腎機能マーカーと腎精の関係について書き進めていきます。
1. 腎精とは?
- 生まれ持った 先天の精(親から受け継ぐ活力)
- 食事や生活習慣で得られる 後天の精
これらが合わさって、成長・発育・生殖・老化のスピードを左右しています。
この考え方は、以前紹介したエピジェネティクスと同じで、遺伝子ですべては決まらないことを表していますね。
つまり、後天の精を養うための食事や生活習慣がいかに大事なのかが分かります。
参考までに過去の記事を載せておきますので、読んでいない方は是非。
2. 腎精と筋肉・タンパク質の関係
分子栄養学的に解釈すると、腎精は「タンパク質やアミノ酸の貯蔵・利用システム」に近い存在と考えることができます。
- クレアチニンが低い → 筋肉量やタンパク質不足
- 慢性的な低タンパク状態 → ホルモン・免疫・代謝すべてが低下
つまり「材料不足で体を維持できない状態」は、東洋医学的には「腎精の消耗」と解釈できるわけなんですね。
人間は外から栄養を取り込まないと生きていけない栄養従属生物ですので、材料は食事として摂り込まなければならないわけです。
つまり、摂取不足をキチンと見極めてアドバイスできないとダメだということがわかると思います。
もちろんいつも書いているとおり、摂っても吸収できなかったり、消費量が多かったりする場合も考慮に入れて、診察・アドバイスを進める必要があります。
3. 老化とのつながり
東洋医学では、腎精は「老化の速度」を決めるものとされ、以下のような症状と関係が深いと考えられています。
- 髪が白くなる
- 歯や骨が弱くなる
- 聴力の低下
- 筋肉減少(サルコペニア)
つまり、これらはすべて腎精不足の典型的なサインであり、栄養学や機能性医学の視点で見れば、タンパク不足や筋肉量の低下が老化を加速させることと一致していると考えることができます。
臨床応用へのヒント
血液検査を「腎精」と結びつけて解釈すると、以下のように臨床に新たな視点を与えてくれます。
- クレアチニンが低い患者
→「腎虚」の背景を疑う必要がある
→栄養指導(タンパク質摂取・アミノ酸補給)+鍼灸治療で補腎をはかることが大事 - BUN/Cr比が高い患者
→「脱水=津液不足」と関連付けて説明することができる
→水分代謝を整える経穴(腎経・膀胱経)や(ミネラルバランスを含めた)生活指導が役立つ - 鍼灸+栄養指導の組み合わせ
→体質改善が進みやすく、治療効果の持続性も高まる可能性が高い
まとめ
腎機能マーカーであるクレアチニン、BUN、BUN/Cr比 は、単なる腎臓の働きだけでなく、
- 筋肉量や栄養状態(特にタンパク摂取)
- 水分バランスや代謝全般
- 東洋医学でいう「腎精」の状態
までも読み解くヒントになることがわかります。
臨床の現場で血液検査をこうした視点で活用できれば、患者さんにより深くて説得力のある説明ができ、栄養指導や鍼灸治療を組み合わせた総合的なアプローチが可能になると考えています。
あなたの腎機能マーカーはどうだったでしょうか?
「腎精の状態」を血液検査から考えてみると、新しい発見があるかもしれません。
今回はこの辺で。