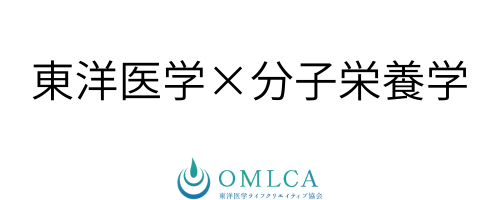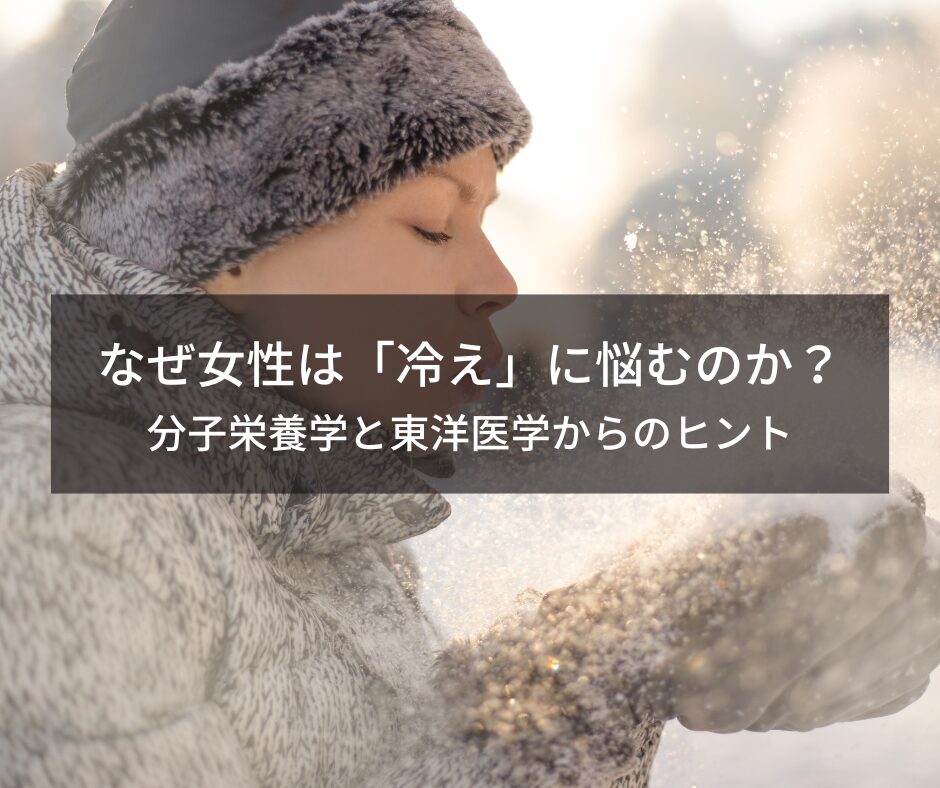分子栄養学と東洋医学からのヒント
「手足が冷えてなかなか眠れない」
「夏でも冷房で体がつらい」
多くの女性が悩む「冷え」は、単なる体質ではなく体からのサインかもしれません。
特にこれだけ暑かった夏も終わって、短い秋から寒い冬へ向かう時期に冷えはこたえますよね。
ということで、今回は「女性の冷え」について書いてみます。
冷えの分子栄養学的な背景
冷えには、いくつかの栄養的な要因が関わっています。
主なものを上げてみると、次の3つが代表的です。
- 鉄不足(貧血)
鉄は酸素を運ぶ役割を持ち、体のすみずみまでエネルギーを届けます。
鉄不足があると細胞が酸欠状態となり、手足まで十分な熱が運ばれません。
女性は月経で鉄を失いやすいため、慢性的な鉄不足が冷えにつながります。
小麦などに鉄を添加している諸外国と比較して、特に日本では鉄不足の女性が多いといわれています。 - タンパク質不足
筋肉は熱を生み出す“工場”です。
タンパク質が足りないと筋肉量が減り、体温を維持しにくくなります。
さらに(血液中のタンパクである)アルブミンが不足すると水分保持力が低下し、血流が悪くなって冷えが助長されます。 - ビタミン・ミネラル不足
ビタミンB群やマグネシウムが不足すると、エネルギーであるATPを産生する力が低下します。
また、亜鉛が不足すると、甲状腺ホルモンの働きが弱まって代謝全般がダウンします。
このように、栄養素の不足も冷えの大きな要因になるんです。
東洋医学から見る冷え
東洋医学では「冷え」を体質やエネルギーの巡りの観点から次のようにとらえます。
- 血虚
血が不足している状態。
体を温める力が足りないため、顔色が青白い・めまい・動悸を伴いやすいです。 - 血瘀
血の巡りが滞っている状態。
血行がわるいため、手足の冷えやしびれ、月経痛などを引き起こしやすいです。 - 腎虚
腎という臓のはたらきが低下している状態。
腎のエネルギーが弱まっているので、全身の基礎代謝や温める力が低下します。
つまり冷えは、「栄養不足による熱産生の低下」+「気血の巡りの乱れ」の両面から考えることが大切なんです。
冷えを和らげるセルフケア
- 鉄とタンパク質を意識した食事 積極的に摂るべき食材は、赤身肉、レバー、牡蠣、イワシなどです。
卵や豆類も良質なタンパク源なので、適度に取り入れましょう。
鉄はビタミンCと一緒に摂ると吸収率がアップします。
具体例としては、レモンを添えたステーキとか、魚とブロッコリーの組み合わせなどがあります。 - エネルギー代謝を助ける栄養素を補う
まず必要なのはビタミンB群です。
多く含まれる食材は豚肉、納豆、玄米など。
次にマグネシウムも欠かせません。
ナッツ、海藻を摂りましょう。
それから亜鉛。
牡蠣、かぼちゃの種などに多く含まれています。 - 「温める」より「巡らせる」習慣
食事以外でもできることはあります。
まずは軽い運動やストレッチで血流を促してください。
朝などに白湯をゆっくり飲むのもいいでしょう。
入浴はシャワーだけでなく、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってじんわり温めましょう。 - 東洋医学的な工夫
それ以外にも生活のなかでちょっとした工夫で冷えを防ぐことができます。
足首やお腹を冷やさないようにしましょう。
深呼吸やヨガなどを取り入れて、「気の巡り」を整える習慣をつけましょう。
生理の前や更年期の不調のときは、なるべく体を締め付けない服装を心がけて、血流を妨げないようにしましょう。
「冷え」は女性にとってとても身近ですが、単なる体質ではなくからだからのサインです。
ただ温めるだけでなく、体の内側から「熱を生み出す力」と「巡らせる力」を育てることが、冷え改善の近道になります。
「私の冷えはどこから来ているんだろう?」と感じたときは、自分の栄養状態や体質を一度チェックしてみるのもおススメです。