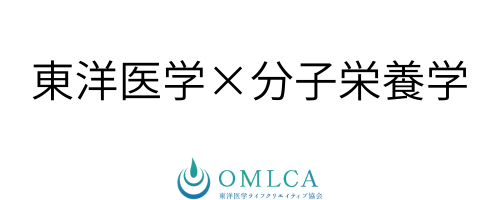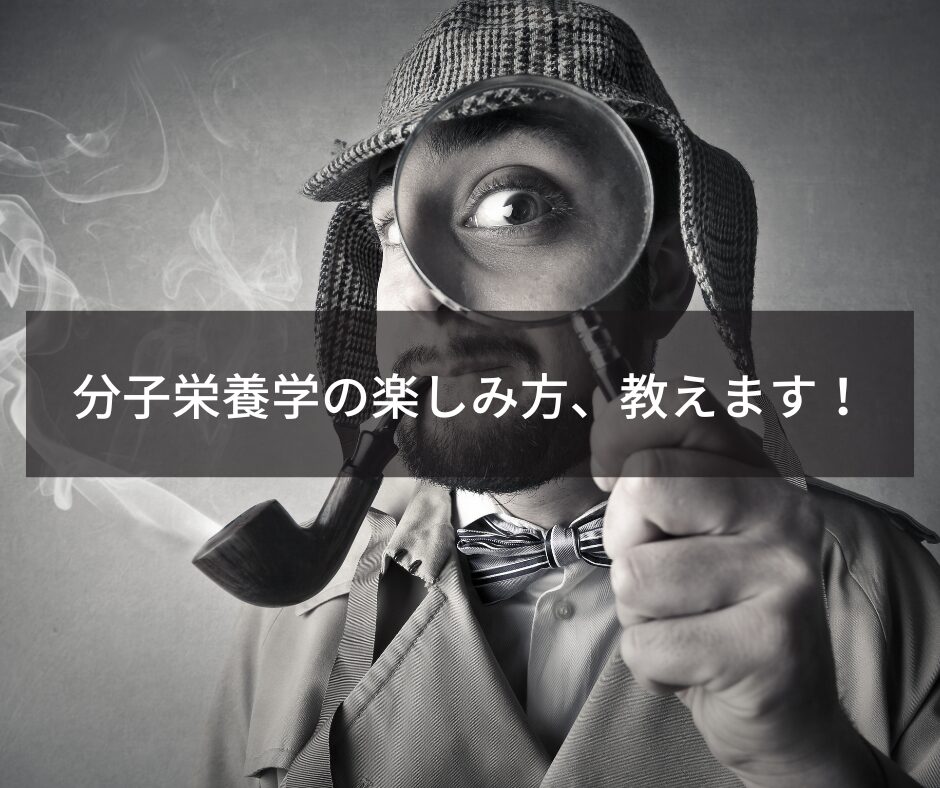いつも読んでいただきありがとうございます。
今日は、僕がどうして分子栄養学にハマっているのかについて書いてみます。
じつは、分子栄養学って探偵みたいなものなんです。
その犯人探しと事件解決の過程が楽しいのでめちゃめちゃハマっています(笑)
僕がやっている犯人探しの過程について、ちょっと見ていきましょう。
分子栄養学って探偵みたいなもの
まずは証拠をいろいろ探します。
これはつまり、栄養の不足やそれを引き起こしている原因を探すってことです。
そして、証拠をそろえて犯人を突き止めます。
これは体に悪さをしている栄養素の過不足を特定するということです。
具体的な方法は、四診+血液データ。
これを栄養学的な側面からいろいろと分析していくわけです。
犯人は一人とは限らなくて、複数の場合が多いです。
複数いる場合は、その中で誰が主犯(つまり根本的な原因)かを考えます。
犯人を特定しただけでは事件は解決しないので、つぎに解決方法を考えます。
その際に、どんな方法と順番で解決していったらよいかを念入りに検討します。
順番を間違えると、犯人を取り逃してしまう可能性もあるので、ここは結構大事なところです。
体をキチンと治していくためには、正しい順番が存在するんですよね。
例えば甘いものが欲しくなる原因が貧血だとすると、「甘いものはカラダに悪いので止めましょう!」というアドバイスをしても、貧血が治っていないので体の欲求として甘いものに手が伸びてしまいます。
だから、治す順番ってとても大事なんです。
順番が決まったら、次はいよいよ犯人を捕まえて取り調べをします。
つまり、栄養や食事で症状の改善をするためのアドバイスをするってことです。
例えば貧血の場合、鉄分が多く含まれている食材は基本的に動物性のタンパク質です。
特に赤みの強いお肉やお魚を摂るようにしてもらいます。
サプリで摂る場合には、ビタミンCと鉄サプリを一緒に摂ると、吸収率が高まることが報告されているので、これを実践してもらいます。
アドバイスによって貧血症状が治って、甘いものがなくてもエネルギー不足にならない体になれば、事件は解決です。
再捜査が必要な場合もあります
ただ、これで問題が解決したかというと、そんな保証はありません。
(探偵の設定なので逮捕はできませんが)誤認逮捕の可能性もあるからです。
ここまでの過程が正しかったかの検証が必要になります。
それはどうするかというと、本当に問題が解決したかを数ヶ月かけてチェックするんです。
具体的には、だいたい3〜4ヶ月後に再チェックをします。
もちろん犯人があたっていたら、問題は解決しているはずです。
つまり患者さんの症状がどのように改善したか、あるいはしなかったかを検証するわけです。
そのための証拠集めをします。 これは問診や切診だけでなく、血液検査をしてもらうとより確実にわかります。
ここでもし最初に目星をつけた犯人が違っていたり、他にも強力な仲間がいることが判明したら、捜査方針を軌道修正します。
例えば貧血が根本的な原因だと思って鉄サプリを摂ってもらったとします。
再検査で貧血は解決したんだけど、じつは貧血の原因にもなっていた胃酸の出の悪さが原因で他のミネラルやタンパク質の吸収が悪かった、なんてこともあったりします。
そうすると、貧血だけを治しても、貧血以外のの症状が改善していないことに気がつきます。
そこで、胃酸の出を良くする食べ方をアドバイスしたり、タンパク質を吸収しやすいアミノ酸の形で摂ってもらったりする必要がでてきます。
タンパク質の吸収が悪いと腸内環境が悪くなりがちなので、お通じをについて詳細に尋ねて状況を把握した上で、腸活のアドバイスをする場合もあります。
そしてついに問題が解決して、「めでたしめでたし〜」となるわけです。
つまり治療が終了するということ。
あとは半年から1年に1回くらい、その後の状態を確認しにきていただくだけですね。
問題がしっかり解決できると再発がしにくくなるので、これもメリットですね。
こんな感じです。
どうですか? 楽しそうじゃないですか?
今回はこの辺で。